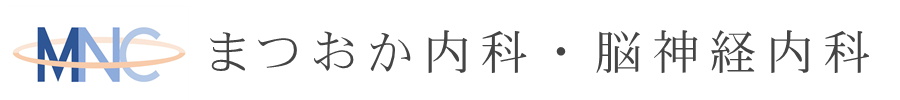2021年8月4日発売の新書です。
フタバ図書の新書コーナーをぶらぶらしていたら、平積みにされていたこの本が目にとまり、タイトルに惹かれてすぐに購入しました。
著者は「大改造!!劇的ビフォーアフター!」に出演したこともある一級建築士なのですが、自ら設計したサ高住の施設長として介護現場の最前線も経験しており、その2つの視点から、1.幸福な最後の居場所とはどのようなものか、2.それをどのように自分で整え準備していけばよいのか、について考察・提案をしています。
第1章:最後の居場所は「自宅」こそふさわしい理由
第2章:「介護施設に入るべきか?」、迷ったときに知っておくべきこと
第3章:それでも知りたい、よい介護施設・老人ホームの見分け方
第4章:最後まで暮らせる安心老後住宅のつくり方
第1章で述べられている著者の考えを抜粋しました。
「病状や親族との関係など、それぞれのご事情があるので実現が難しい場合もあることを承知のうえであえて言わせていただければ、私は最後の居場所は、病院や介護施設ではなく、自宅こそがふさわしいと考えている。(p20)」
「それぞれの場所(介護施設)に、それぞれ必要とされる理由があるのは確かだが、住環境の専門家として見てみると、自分らしい理想的な最後の居場所としてもっとも適しているのは自宅だと言える。(p67~68)」
「自宅とホスピス以外では少なくとも居住空間としては、穏やかでゆったりとした時間のなかでの最後を迎えることは不可能である。これが、建築士であり、かつ介護施設長を務め、いくつかの看取り経験もしてきた私の結論である。(p68)」
第2~3章では、ウラ事情まで含めた介護施設の実際について解説してあります。
第4章では、自宅を終の住処とするための方法論について述べてあり、具体的で非常に参考になりました。
介護施設に入ろうか悩んでいる人や親の介護が必要となってきている人は、一度本書に目を通して筆者の経験や考えを参考にしてみてはいかがでしょうか。
「終の住処」として介護施設を選択するときは慎重に・・・
「介護が必要になったら自分は最後は施設に入るつもり」、「親の一人暮らしは心配なので、いずれは施設に入れることを考えている」、という話をよく耳にします。
しかし、自分あるいは家族の人生の最後を迎える場所として選ぶ「介護施設」というものについて、十分に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
一言で介護施設といっても、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、など多くの種類があり、それぞれ入居できる基準、費用、介護体制、医療へのアクセスなどが異なります。
これらの施設の特長や欠点を全て理解した上で、どの種類の施設が自分や家族に合っているかを考えることは、医療・介護関係者であっても簡単なことではありません。
さらに、同じ種類の施設であっても、経営する法人の方針やスタッフの質によって介護の質はピンキリとなるため、そこでの生活に満足できるかどうかは、実際に入居してみないとわからないのです。
もし「自分に合ったよい施設」にたまたま入居できたとしても、優秀で献身的なスタッフがいなくなったり、施設長が代わったりすることで、「自分に合わない最悪の施設」に早変わりしてしまうことも珍しいことではありません。
また、そもそも看取りに対応していない施設であれば、最後をそこで迎えることはできません。穏やかに自然に逝きたいと思っていても、他施設や病院への移動を余儀なくされるでしょう。
「終の住処」についての相談を受け付けています
・できれば住み慣れた自宅で最後まで過ごしたい
・病院や施設のルールに縛られず自宅で自由に生活したい
・自宅で本当に生活を続けられるのか不安
・家族に施設を勧められているが、本当にそれでよいのか・・・
上記の思いや不安をお持ちの方は、お気軽に当院にご連絡ください。
要介護の状態で自宅で生活していくためには、多くの知識、経験、そして工夫が必要です。
自宅で穏やかに過ごせるよう、精一杯お手伝いいたします。
元気なうちに「終の住処」について話し合ってください
終の住処について考えるということは、どう生きて、どう逝くのか、を考えることになります。
そしてそれは、「人生会議(ACP:Advance Care Planning)」(人生の最終段階においてどのような医療やケアを望むのか話し合っていくプロセス)へとつながっていくのです。
今は健康であったとしても、人はいずれは死を迎えます。
交通事故、感染症、癌、脳卒中、心疾患、難病、老衰・・・。
自分、あるいは家族が意思表示できない状態となったとき、治療やケアの方針はどのように決定していくのでしょうか?
ACPを行っている場合、本人の死生観に沿った意思決定支援が可能となります!
「終の住処」について話し合うことは、自分や家族の死生観を見つめ直すきっかけとなるでしょう。